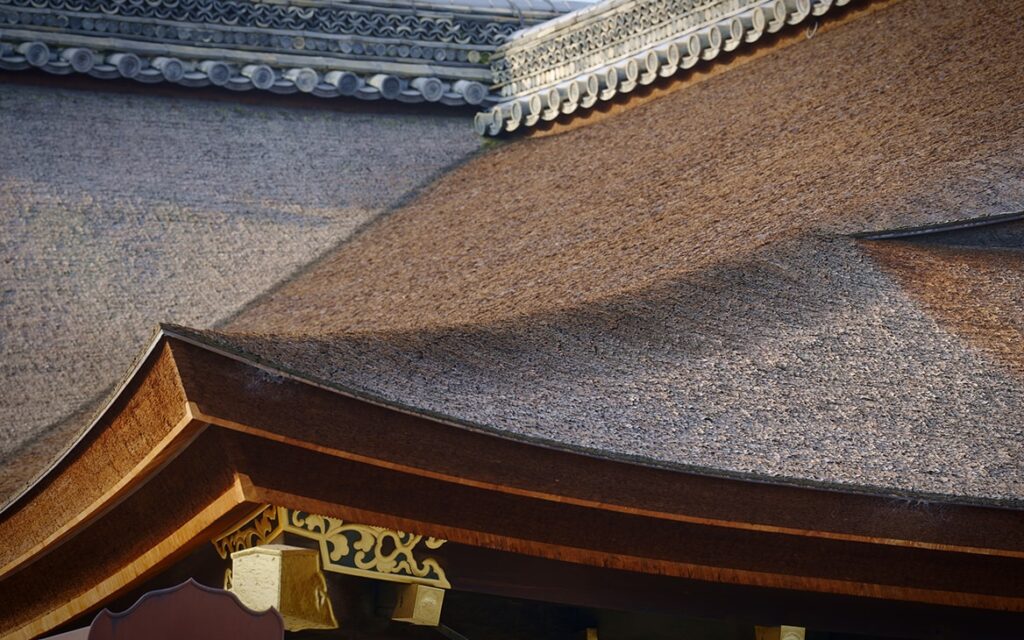東寺は京都で最も古い寺院です。 桓武天皇(735-806)が平安京に遷都してから2年後の796年に国家鎮護のために建立されました。 当時、都の内側に建てることを許された寺院は2つしかなく、東寺はそのうちの1つでした。 ”東寺“という名前のとおり、この寺院は当時の都の正門の東側に位置しています。 もう一つの寺院、西寺は1233年に火災で焼失しその後再建されることはありませんでした。 東寺は、弘法大師(仏教の教義の大師の意)として知られる空海(774–835)と深い関わりがあります。 空海は遣唐使の一員として804年に中国に渡り、唐代(618-907)にインドから中国に広まった密教の教義と儀式を学びました。 空海は806年に帰国し、中国で学んだことを日本で伝え始めました。 823年、嵯峨天皇(786–842)は東寺を空海に下賜し、別当に任じます。 この時期頃までに空海は、自らの教義を真言宗として体系化していました。 空海は、東寺において真言宗の教えのみが実践されることを条件に、別当の職に就きました。 これは、一つの寺院で複数の宗派が奉じられていた当時の一般的な慣行からの大胆な脱却でした。 空海は東寺に中国から持ち帰った曼荼羅や宝物を納め、また講堂や五重塔などの新しい建造物を建て、東寺を真言密教の根本道場としました。 京都の他の寺院と同様に、東寺も1200年以上にわたって火災、地震、戦乱、その他の災害を乗り越えてきました。 建造物の多くは、一度ならず何度も再建されています。そうして東寺は約1200年にわたり、空海の教えとともに諸堂や仏像などの宝物を守り伝えてきました。 東寺は、古都京都の文化財の一部として、1994年、ユネスコにより世界文化遺産に指定されています。
閉じる
縁側
身舎(もや)の外側に設けた板敷の通路部分を指す。格式のある座敷の縁は、広縁としさらに落縁(おとしえん)を設けて広く開口部を開ける。
この言葉が使われている文化遺産
閉じる
竹の節欄間
鎌倉から室町頃に普及した欄間のひとつ。 竹の節のような切れ込みをつけた親柱に、玉縁と呼ばれる横架材を渡し、その中を山形もしくはたすきがけの桟で埋めた、質素な印象の欄間。
この言葉が使われている文化遺産
閉じる
書院造
座敷飾と呼ばれる設備を備えた座敷や建物を広く呼ぶようになったもの。格式を重んじ、対面・接客の機能を重視してつくられ、書院造りの様式は現代に受け継がれており、和室の原型と言える。
この言葉が使われている文化遺産
閉じる
安土桃山時代
時代区分の一つ。織田信長が足利義昭を奉じて入京した1568年から豊臣秀吉が亡くなった1598年、または徳川家康が征夷大将軍に任じられ幕府を開いた1603年までを指す。
この言葉が使われている文化遺産
閉じる
宮本武蔵
江戸時代初期の剣客。1584~1645。兵法家、芸術家。二刀を用いる二天一流兵法の祖。京都の兵法家・吉岡一門との戦いや巌流島での佐々木小次郎との決闘が有名。
この言葉が使われている文化遺産
閉じる
真言八祖
真言密教の法を伝え護持したインド・中国・日本の僧侶8人。龍猛(りゅうみょう)・龍智(りゅうち)・金剛智(こんごうち)・不空(ふくう)・善無畏(ぜんむい)・一行(いちぎょう)・恵果(けいか)・空海(くうかい)のこと。
この言葉が使われている文化遺産
閉じる
五智如来
大日如来が備える五種の智慧を、金剛界の五如来にそれぞれの智が配せられたものと言われる。金剛界の五智如来は、大日如来・阿閦如来・宝生如来・阿弥陀如来・不空成就如来の五体である。
この言葉が使われている文化遺産
閉じる
心柱
仏塔の中心に据える柱で心礎の上に立ち、頂部まで通り屋根の上の相輪を支える。仏舎利を納める場所を示す象徴的な意味合いがあると言われる。
この言葉が使われている文化遺産
閉じる
仏舎利
仏陀の遺骨のことを指し、舎利を供養する習慣から舎利信仰に発展。日本伝来後も仏塔に舎利を祀る舎利信仰が盛んとなり、五重塔や三重塔などが建立された。
この言葉が使われている文化遺産
閉じる
徳川
ここでは徳川幕府(江戸幕府)のこと。1603年(慶長8年)、徳川家康が征夷大将軍に補任され、江戸(東京)を本拠として創立した15代続く武家政権。徳川家が将軍職を世襲した。大政奉還が行われた1867年(慶応3年)までの約264年間とされる。
この言葉が使われている文化遺産
閉じる